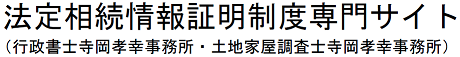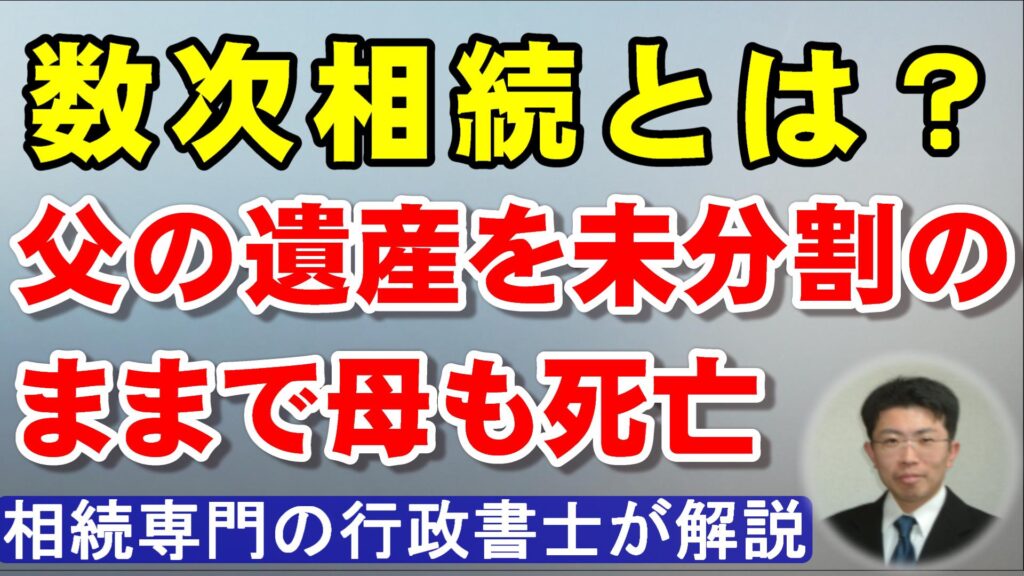行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。
経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。
行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら
法定相続(ほうていそうぞく)とは、
被相続人(亡くなった方)の遺言書がない場合に、
民法で定めている相続人と相続分で遺産分割することです。
そして、民法で定めている相続人のことを法定相続人といい、
民法で定めている相続分のことを法定相続分といいます。
まず、法定相続人については、下表1のように、
常に相続人になる被相続人の配偶者(夫または妻)と、
第一順位から第三順位の相続人が民法で定められています。
| 法定相続人の範囲 | |
|---|---|
| 常に相続人になる人 | 被相続人の配偶者(夫または妻) |
| 第一順位の相続人 | 被相続人の直系卑属(子供、孫、ひ孫以下) |
| 第二順位の相続人 | 被相続人の直系尊属(父母、次の順位として祖父母) |
| 第三順位の相続人 | 被相続人の兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥姪) |
第一順位から第三順位の内、
異なる順位の相続人が、同時に相続人になることはなく、
順位が先でなければ相続人にはなれません。
次に、法定相続分については、被相続人に配偶者がいる場合といない場合、
第一順位から第三順位の相続人のいるいないによって、
下表2のように民法で定められています。
| 配偶者 | 第一順位(子供等) | 第二順位(父母等) | 第三順位(兄弟姉妹) |
|---|---|---|---|
| 2分の1 | 2分の1 | 相続分0 | 相続分0 |
| 3分の2 | いない | 3分の1 | 相続分0 |
| 4分の3 | いない | いない | 4分の1 |
| いない | 全部相続 | 相続分0 | 相続分0 |
| いない | いない | 全部相続 | 相続分0 |
| いない | いない | いない | 全部相続 |
| 全部相続 | いない | いない | いない |
ただし、それぞれの方が相続放棄することも可能なため、
上表2の法定相続分のとおりにしなければならないということではありません。
亡くなった方の遺言書がない場合に、
民法で定められた法定相続分は目安になりますが、
最終的には、法定相続人全員の話し合いで相続分を決めることになるからです。
法定相続人全員の話し合いの結果、
法定相続人の1人がすべての遺産を相続することも可能ですし、
各法定相続人が法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。
ただ、亡くなった方の遺言書がない場合には、
民法で定められた法定相続人以外の人に、
遺産を相続させることはできませんので注意が必要です。
また、第一順位、第二順位、第三順位の法定相続人がそれぞれ複数人いる場合、
その順位と人数によって、法定相続分が変動します。
そこで、第一順位、第二順位、第三順位の各法定相続人が、
複数人いる場合の法定相続も含めて、配偶者がいる場合といない場合、
そして、各順位ごとの法定相続についてわかりやすくご説明致します。
配偶者と第一順位(子供、孫)の法定相続
被相続人(亡くなった方)に配偶者と子供がいれば、
配偶者と子供が法定相続人となり、
法定相続分は、配偶者が2分の1、子供全員で2分の1です。
もし、子供が複数人いるときは、
子供全員で2分の1の法定相続分を、
子供の人数で均等に割ります。
例えば、下図1のように、亡くなった方の子供が3人いた場合、
法定相続分については、配偶者が2分の1、
子供全員で2分1(子供1人あたり6分の1)となります。
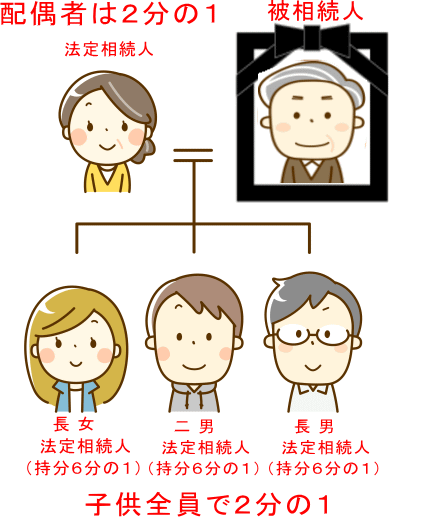
被相続人に配偶者がいて、第一順位の子供が複数人いた場合について、
子供1人あたりの法定相続分の早見表を下記に記載しておきます。
| 子供が2人いた場合 | 配偶者2分の1 | 子供1人あたり4分の1ずつ |
| 子供が3人いた場合 | 配偶者2分の1 | 子供1人あたり6分の1ずつ |
| 子供が4人いた場合 | 配偶者2分の1 | 子供1人あたり8分の1ずつ |
| 子供が5人いた場合 | 配偶者2分の1 | 子供1人あたり10分の1ずつ |
また、第一順位の子供の内で、すでに亡くなっている子供がいた場合には、
下図2のように孫が代わりに法定相続人となり、
法定相続分もそのまま代襲(だいしゅう:代わりに引き継ぐこと)されます。
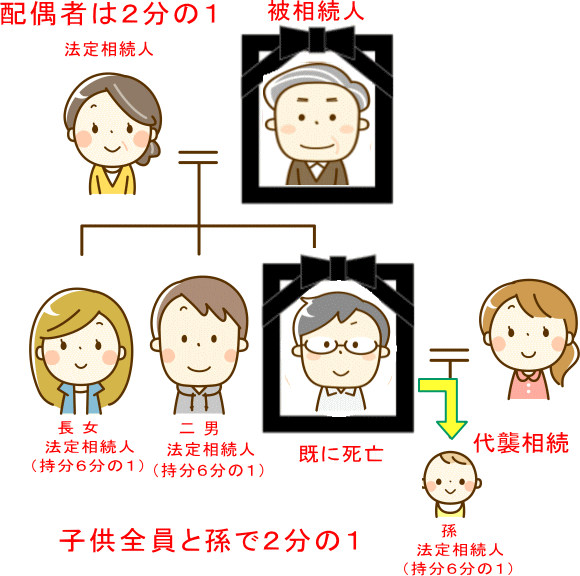
孫が代わりに相続することを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
もし、孫もすでに亡くなっている場合には、
ひ孫が代わりに法定相続人となるのです。
逆に、下図3のように、既に亡くなっている子供に子がいない場合には、
残りの子供全員で2分の1で均等割りになるため、
子供1人あたり4分の1ずつとなります。
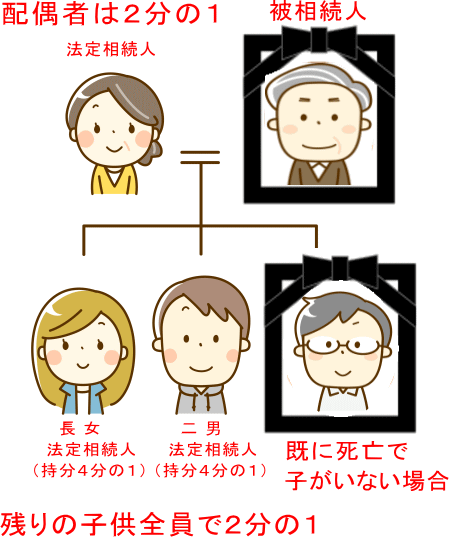
なお、法定相続情報証明制度を利用する場合に、
配偶者と子供が法定相続人の「法定相続情報一覧図」の見本については、
「法定相続情報一覧図の見本」のページを参照ください。
第一順位(子供、孫)のみの法定相続
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいなくて、
第一順位(子供、孫、ひ孫など直系卑属)がいる場合には、
第一順位だけが法定相続人となり、法定相続分は全部です。
ただし、第一順位の中でも優先順位があり、
最優先は子供、子供が1人もいない場合に孫、
子供も孫も1人もいない場合にひ孫、という順番で法定相続人になります。
つまり、子供が1人でもいれば、
代襲相続や数次相続、遺言書の場合を除いて、
孫やひ孫は相続人になれないということです。
そして、子供が複数人いるときの法定相続分は、
子供の人数で均等割りとなります。
たとえば、下図4のように子供が3人なら、
子供3人で均等に割って、
それぞれの法定相続分は3分の1ずつになります。
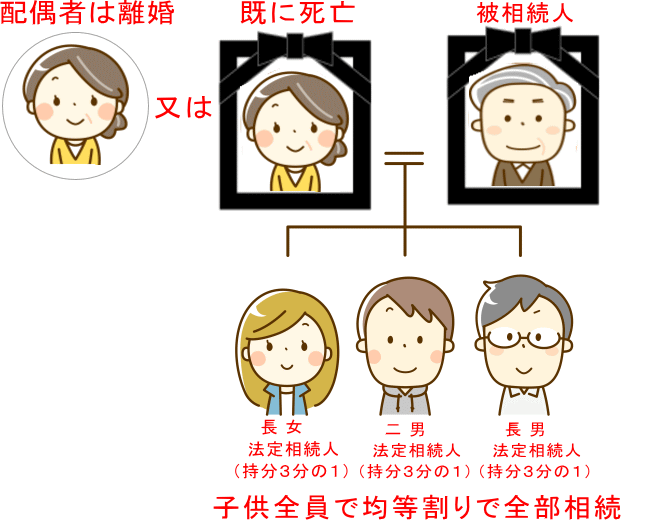
次に、子供の内で、既に亡くなっている子供がいた場合、
その子供に子がいなければ、
下図5のように、残りの子供全員で均等割りで全部相続することなります。
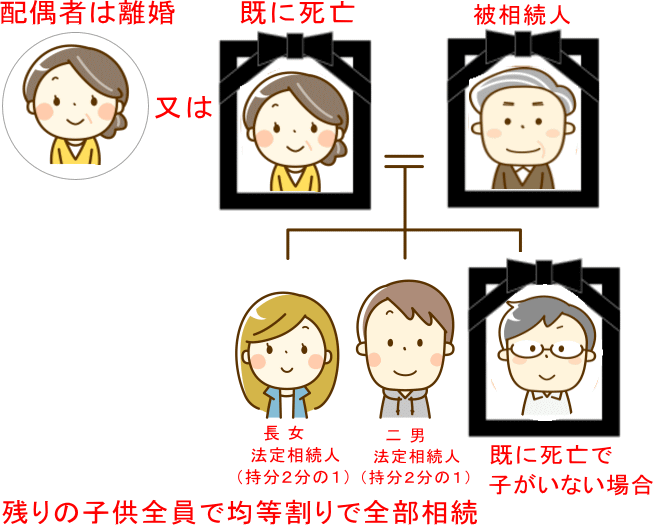
しかし、既に亡くなっている子供に子がいれば、
下図6のように、孫がその法定相続分をそのまま代襲相続します。
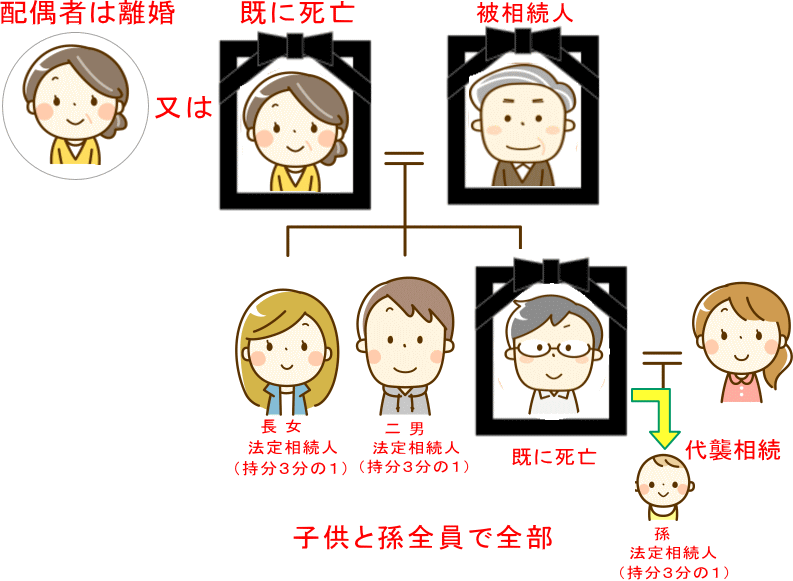
なお、代襲相続(だいしゅうそうぞく)や、
数次相続(すうじそうぞく)については、
「代襲相続とは」や「数次相続とは」のページを参照ください。
また、法定相続情報証明制度を利用する場合に、
子供のみが法定相続人の「法定相続情報一覧図」の見本については、
「法定相続情報一覧図の見本」のページを参照ください。
配偶者と第二順位(父母、祖父母)の法定相続
被相続人(亡くなった方)に子供や孫がいなくて、
配偶者と第二順位(父母や祖父母など直系尊属)がいる場合、
配偶者と第二順位(①父母、②祖父母等)が法定相続人となり、
法定相続分は、配偶者3分の2、第二順位の相続人3分の1です。
ただし、第二順位の中でも優先順位があり、
最優先は父母、父母が両方既に亡くなっている場合のみ、
祖父母が相続人になれます。
具体的には、下図7のように亡くなった方の父母のどちらかが生きていれば、
祖父母は相続人になれないということです。
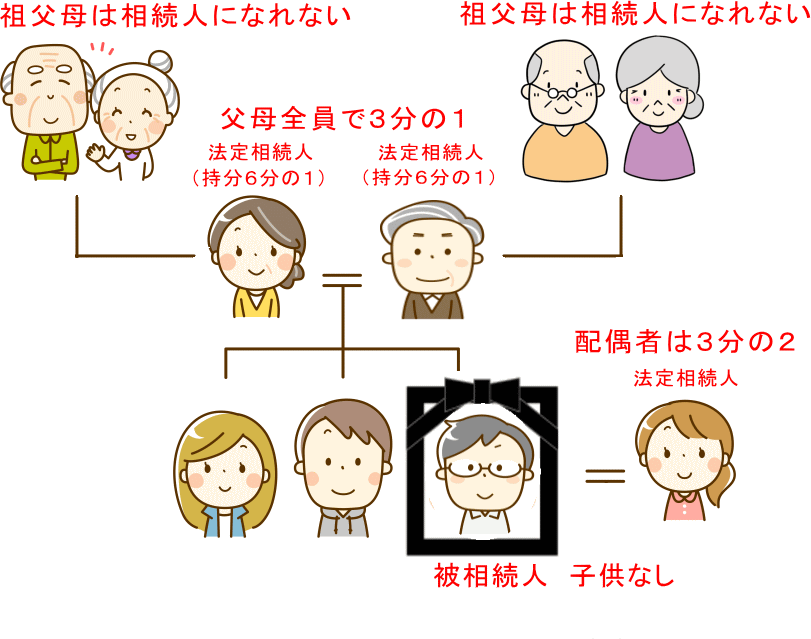
被相続人に配偶者がいて、第二順位の父母や祖父母が複数人いた場合について、
第二順位の相続人になれる人と法定相続分の早見表を下記に記載しておきます。
| 配偶者 | 父 | 母 | 祖父 | 祖母 |
|---|---|---|---|---|
| 3分の2 | 3分の1 | 亡 | 相続分0 | 相続分0 |
| 3分の2 | 亡 | 3分の1 | 相続分0 | 相続分0 |
| 3分の2 | 6分の1 | 6分の1 | 相続分0 | 相続分0 |
| 3分の2 | 亡 | 亡 | 3分の1 | 亡 |
| 3分の2 | 亡 | 亡 | 亡 | 3分の1 |
| 3分の2 | 亡 | 亡 | 6分の1 | 6分の1 |
なお、法定相続情報証明制度を利用する場合に、
配偶者と第二順位(父母等)が相続人の「法定相続情報一覧図」の見本については、
「法定相続情報一覧図の見本」のページを参照ください。
第二順位(父母、祖父母)のみの法定相続
被相続人(亡くなった方)に配偶者も子供も孫もいなくて、
第二順位(父母や祖父母など直系尊属)がいる場合、
第二順位(①父母、②祖父母等)のみが法定相続人となり、
法定相続分は全部です。
ただし、第二順位の中でも優先順位があり、
最優先は父母、父母が両方既に亡くなっている場合にのみ、
祖父母が相続人になれます。
具体的には、下図8のように亡くなった方の父母のどちらかが生きていれば、
祖父母は相続人になれないということです。
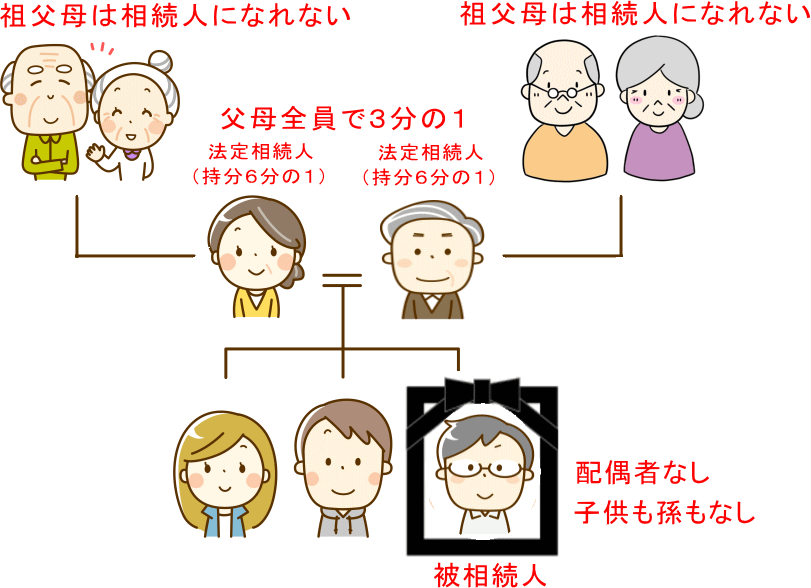
次に、第二順位の父母や祖父母が複数人いた場合について、
第二順位の相続人になれる人と法定相続分の早見表を下記に記載しておきます。
| 父 | 母 | 祖父 | 祖母 |
|---|---|---|---|
| 全部相続 | 亡 | 相続分0 | 相続分0 |
| 亡 | 全部相続 | 相続分0 | 相続分0 |
| 2分の1 | 2分の1 | 相続分0 | 相続分0 |
| 亡 | 亡 | 全部相続 | 亡 |
| 亡 | 亡 | 亡 | 全部相続 |
| 亡 | 亡 | 2分の1 | 2分の1 |
つまり、被相続人(亡くなった方)の父母のどちらかが生きていれば、
生きている方が全部相続し、
祖父母は相続人にはなれないということです。
被相続人の父母が共に生きていれば、
均等に割ったものが法定相続分(父母それぞれ2分の1ずつ)となり、
祖父母は相続人にはなれません。
そして、父母の両方が既に亡くなっていて、
祖父母が生きていれば、祖父母は相続人になれるのです。
なお、ここで言う父母には、実父母だけでなく、
戸籍上の養親(養父母)も含まれます。
配偶者と第三順位(兄弟姉妹、甥姪)の法定相続
被相続人(亡くなった方)に子供や孫がいなくて、
直系尊属(父母や祖父母)も全員既に亡くなっている場合、
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となり、
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。
もし、兄弟姉妹が複数人いるときには、下図9のように、
兄弟姉妹全員で4分の1の法定相続分を均等に割ります。
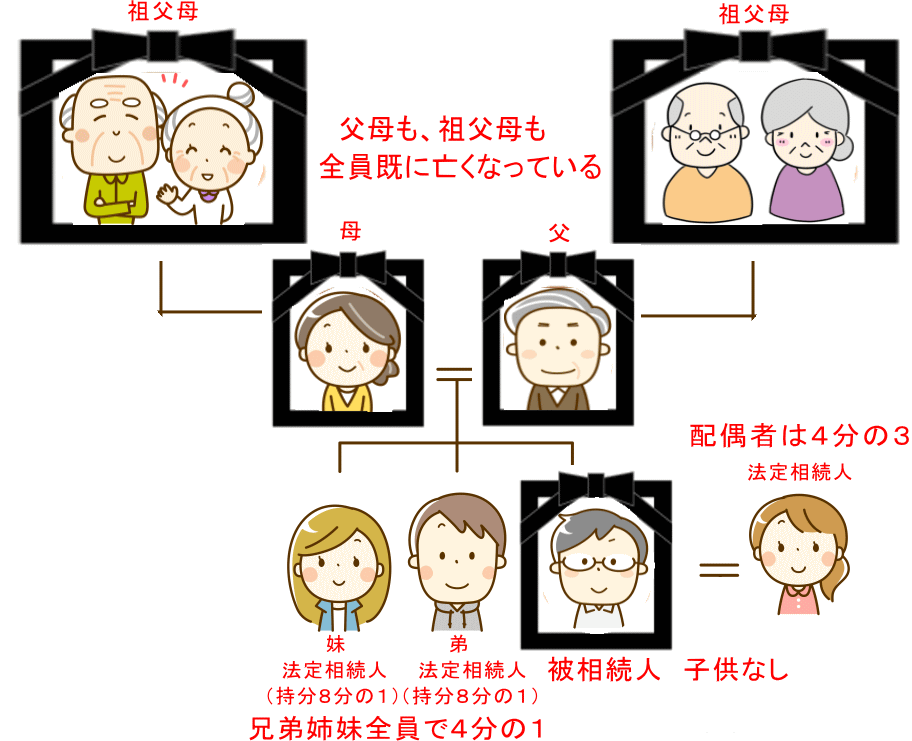
次に、第三順位の兄弟姉妹が複数人いた場合について、
法定相続分の早見表を下記に記載しておきます。
| 兄弟姉妹が2人いた場合 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹1人あたり8分の1ずつ |
| 兄弟姉妹が3人いた場合 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹1人あたり12分の1ずつ |
| 兄弟姉妹が4人いた場合 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹1人あたり16分の1ずつ |
| 兄弟姉妹が5人いた場合 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹1人あたり20分の1ずつ |
| 兄弟姉妹が6人いた場合 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹1人あたり24分の1ずつ |
| 兄弟姉妹が7人いた場合 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹1人あたり28分の1ずつ |
また、被相続人の兄弟姉妹の内で、すでに亡くなっている方がいた場合、
その兄弟姉妹に子供(被相続人の甥姪)がいれば、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の代わりに法定相続人となり、
下図10のように、法定相続分もそのまま引き継ぎます。
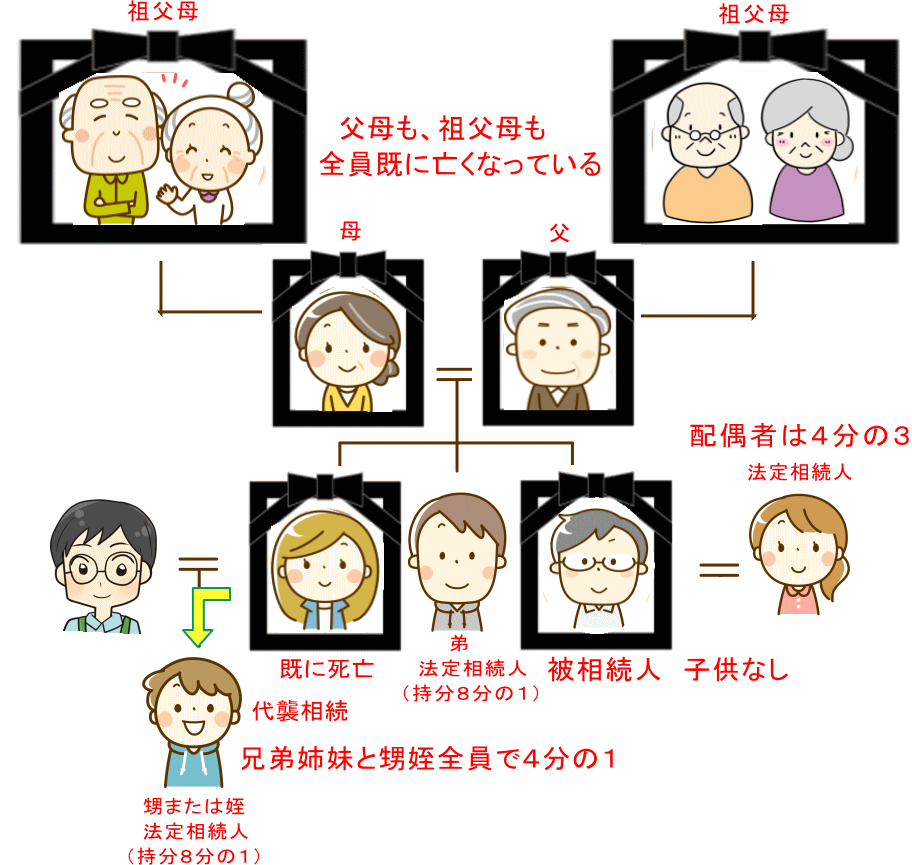
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、
代わりに相続人になる甥姪のことを代襲相続人ともいいます。
第三順位(兄弟姉妹、甥姪)のみの法定相続
被相続人(亡くなった方)に配偶者や子供や孫もいなくて、
直系尊属(父母や祖父母)も全員既に亡くなっている場合、
被相続人の兄弟姉妹のみが法定相続人となり、
法定相続分は兄弟姉妹全員で全部です。
もし、兄弟姉妹が複数人いるときには、
下図11のように、兄弟姉妹全員で均等に割ります。
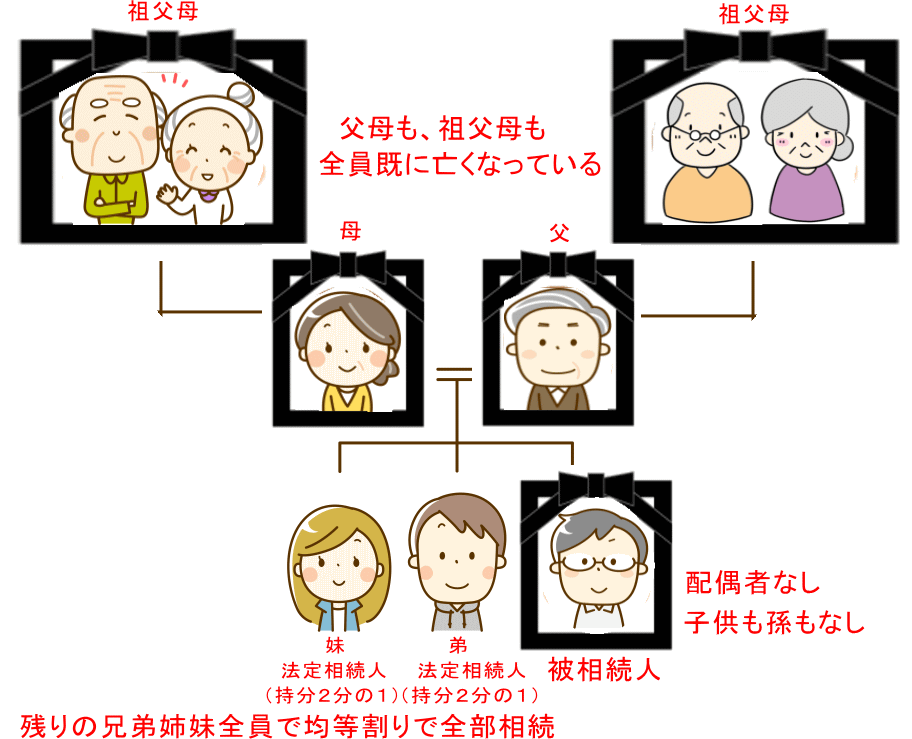
また、被相続人の兄弟姉妹の内で、すでに亡くなっている方がいた場合、
その兄弟姉妹に子供(被相続人の甥姪)がいれば、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の代わりに法定相続人となり、
下図12のように、法定相続分もそのまま引き継ぎます。
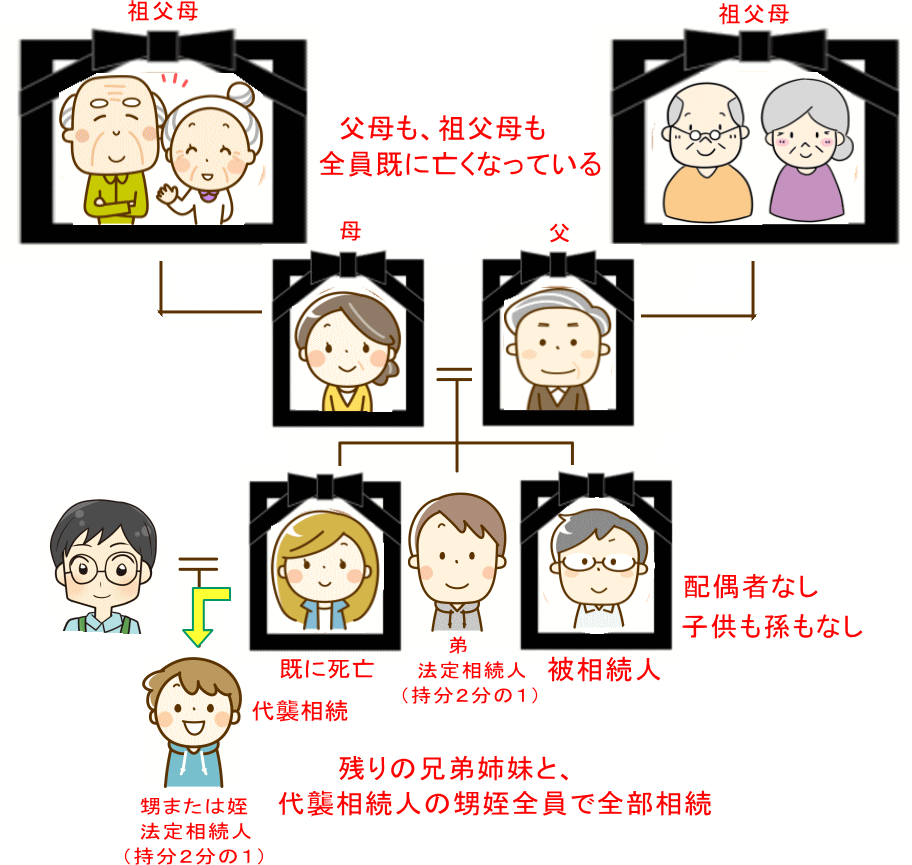
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の代わりに相続人になる甥姪を、
代襲相続人ともいいます。
配偶者のみの法定相続
下図13のように、被相続人(亡くなった方)に子供や孫がいなくて、
直系尊属(父母や祖父母)も全員既に亡くなっていて、
兄弟姉妹や甥姪もいない(又は亡くなっている)場合、
配偶者がいれば、配偶者のみが法定相続人となり、法定相続分は全部です。
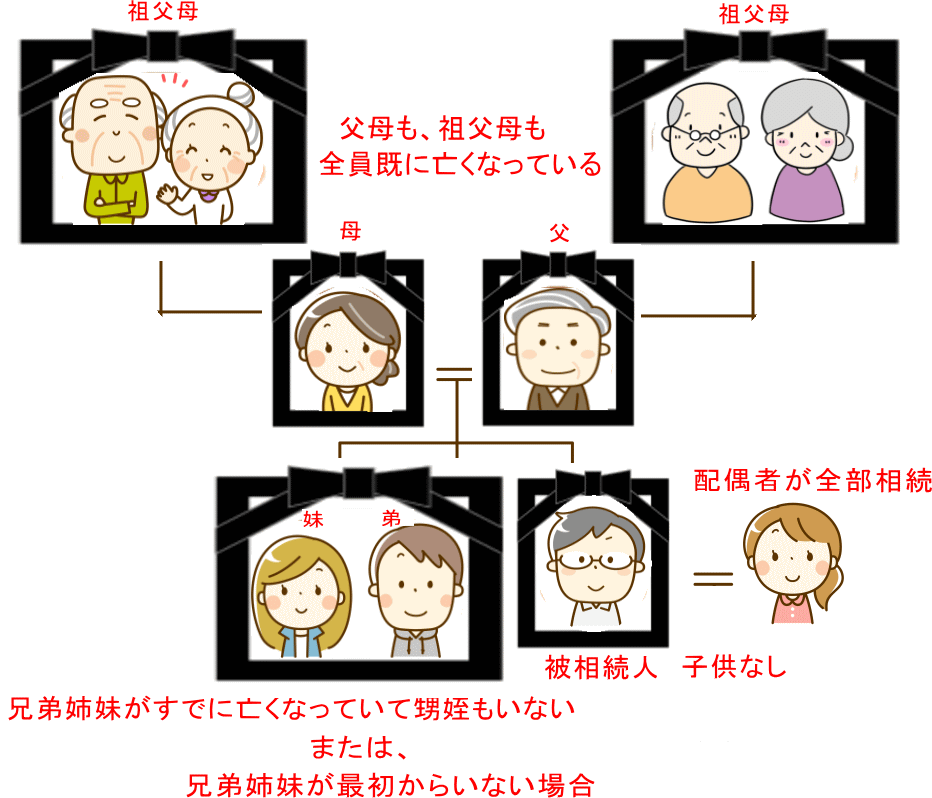
法定相続についての補足
被相続人の遺言書が無い場合や、
遺言書の内容と異なる内容で遺産分割する場合には、
法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
法定相続人の全員が参加していない遺産分割協議は、
無効になるのが原則だからです。
そして、法定相続人全員を明らかにできるのは、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、
相続関係者の戸籍謄本等です。
そのため、戸籍謄本等を役所で取得してから、
取得した戸籍謄本等の内容を正確に読み込み、
法定相続人の特定を最初に行う必要があるのです。